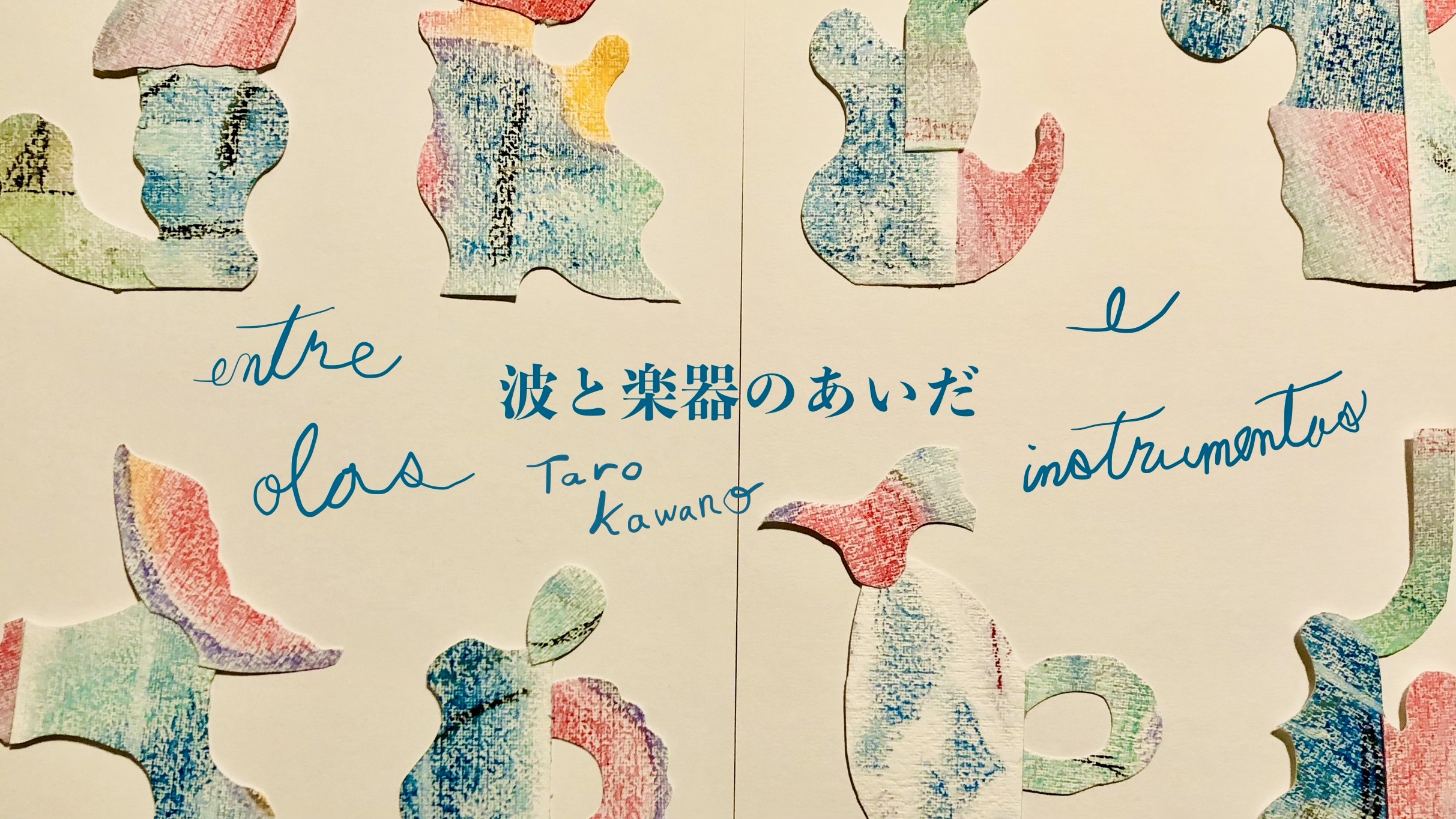
川野太郎
波と楽器のあいだ / 2
2025年9月13日
まなざし
八月最後の日、ちょっと久しぶりにチャリチョコが来て、
「どうした」
「うーん、なに書いていいかわかんなくなった」ぼくは言った。
「え、もう?」
「もう」
「ほんとに?」
「ほんとにって?」
「ほんとになにも書いてないの?」
「や、昨日までに2000字くらいのをふたつくらい書いたんだけど、なんかよくない気がして」
それだけではなかった。詩のようなもの(いまのぼくはそれを詩と断言できない)も別にふたつ書いた。いや、そのうちひとつはギターでコードを鳴らしながら歌として作った。だから、こっちは詩というより歌詞か。詩と歌をひとつずつ作った。
「どれも外に出さないの」
「うーん、なんかどれもつまんないような気がして」
「でもさ、きみの判断力はほんとに当てにならないじゃん。色褪せて見えたものがぜんぶそれなりにいいと思えることもしょっちゅうでしょ」
「それはそうだけど」
「『白紙を埋めるだけならだれにでもできる』とか思ってるんじゃない」
「そうだね」そういう手厳しいことを言うやつがたびたびぼくのなかに戻ってくる。
「いまも『一丁前にスランプか? たいして書いてないくせに』とか思ってる」
絶句するしかない。
「見せてみ」
「え?」
「見せてみ、歌つけたほうの詩」
「うん。これ。あとスマホのボイスメモの一番新しい録音が、実際に弾き語りしたやつ」
「はいはい。あと、おれが読むあいだ、机の上、片付けてよ。この澱んだ空気がそのまま出た机の上を」
「わかった」ぼくはソファーの前にあるローテーブルから、昨日買った団子が入っていたトレーを持ち上げ、情けない気持ちで流しに持って行った。本(六冊)、絵葉書(三枚)、絶縁テープ、海岸で拾った石ころ、はさみ、スケッチブック、しょうゆのボトル、プラスドライバー、裁縫箱、仰向けで寝ているハリネズミのフィギュアを片付けた。
「どう?」ぼくはテーブルをウエットティッシュで拭きながらおそるおそる訊いた。
「もう一回」とチャリチョコは言い、またボイスメモを聴いた。部屋に歌が流れ、ぼくはその歌にたいしてどんな判断もできない。
でも、そのときふと、それが歌なのは疑えない、とも思った。
すると、紙の上の友だちであるチャリチョコは、無造作に歌詞をここに広げた。
「まなざし」
なみの
おとを
きいたら
こえを
わすれたよ
いしと
みずの
さかいめで
ギター、
ひく
もりを
あるいたら
おんがくが
きこえたよ
なつと
あきの
あいだで
ラジオ、
きく
たくさんはなれておいでよ
あしあとはきえないけれど
たどりついたまなざしが
きいた、ねむいですか
それから、コードも。
C―Cmaj7―Dm7―Gsus4―G
(なみのおとをきいたら)
C―Cmaj7―Dm7―Gsus4―G
(こえをわすれたよ)
F―G―C―F
(いしとみずのさかいめで)
C―G―C
(ギター、ひく)
「太郎さ」
「うん」
「これは歌なのは間違いないよね?」
「そうだね」
「だったら、作ったのが自分だからって、質が高いとか低いとか言って消したり残したりできると思うのはくだらないよ」そう言うチャリチョコの目は―――目があるとして―――急に赤くぎらついた。
「お前はそんなに偉いのか?」とチャリチョコは言った。
*
ぼくはお湯を沸かして友達からもらった紅茶を淹れ、チャリチョコが持ってきてくれた梨を切った。いつからか、梨を食べてそのみずみずしい冷たさと甘さを感じたとき、梨に水分があるのではなく、梨が水の本来の姿をつたえている、と錯覚するようになった。これが水の素晴らしさだと。
八月という月を越えると意識して、めったに買わない梨を買って食べたり、すこし遠くの土地の海を眺めに行ったりすることで、われわれは気温こそほとんど昨日と変わらない明日からの日々をやや早めに晩夏と呼ぶことにし、秋に向かう傾斜を進んでいることに決める、とか思った(でも、ほんとうに秋に向かっていると感じるときもあるのだ!)。
「昼の気温は36度だが今日はなにかが違う! 風とか雲の形とかが……とか毎年言ってるもんね。それもひと夏に何回も」とチャリチョコが言った。
「そうなんだよ」ぼくはさっき片付けた本の一冊をまた取り出した。ロシアの詩人ボリース・パステルナークの『晴れよう時』という詩集で、秋についての詩もけっこう入っている。「黄金秋」という詩はこんな感じ。
秋は 誰にでも開かれ見渡せる
おとぎばなしのやうな宮殿
みづうみたちに見惚れた
林道の伐開帯
展覧会場にゐるやうだ
未曾有の金鍍金(きんめっき)をした
ニレ トネリコ ヤマナラシたちの
大広間 大広間 大広間
(…)
秋は 古い書物や 衣装や武器の
古代(いにしへ)の一室
ここでは厳しい寒さが
財宝のカタログの頁をめくつてゐる
ロシアの秋から顔を上げると、いや、やっぱりまだまだ夏か、と思う。ふしぎとうんざりする気持ちは減っている。
*ボリース・パステルナーク『晴れよう時 1956-1959』工藤正廣訳、未知谷、2004年
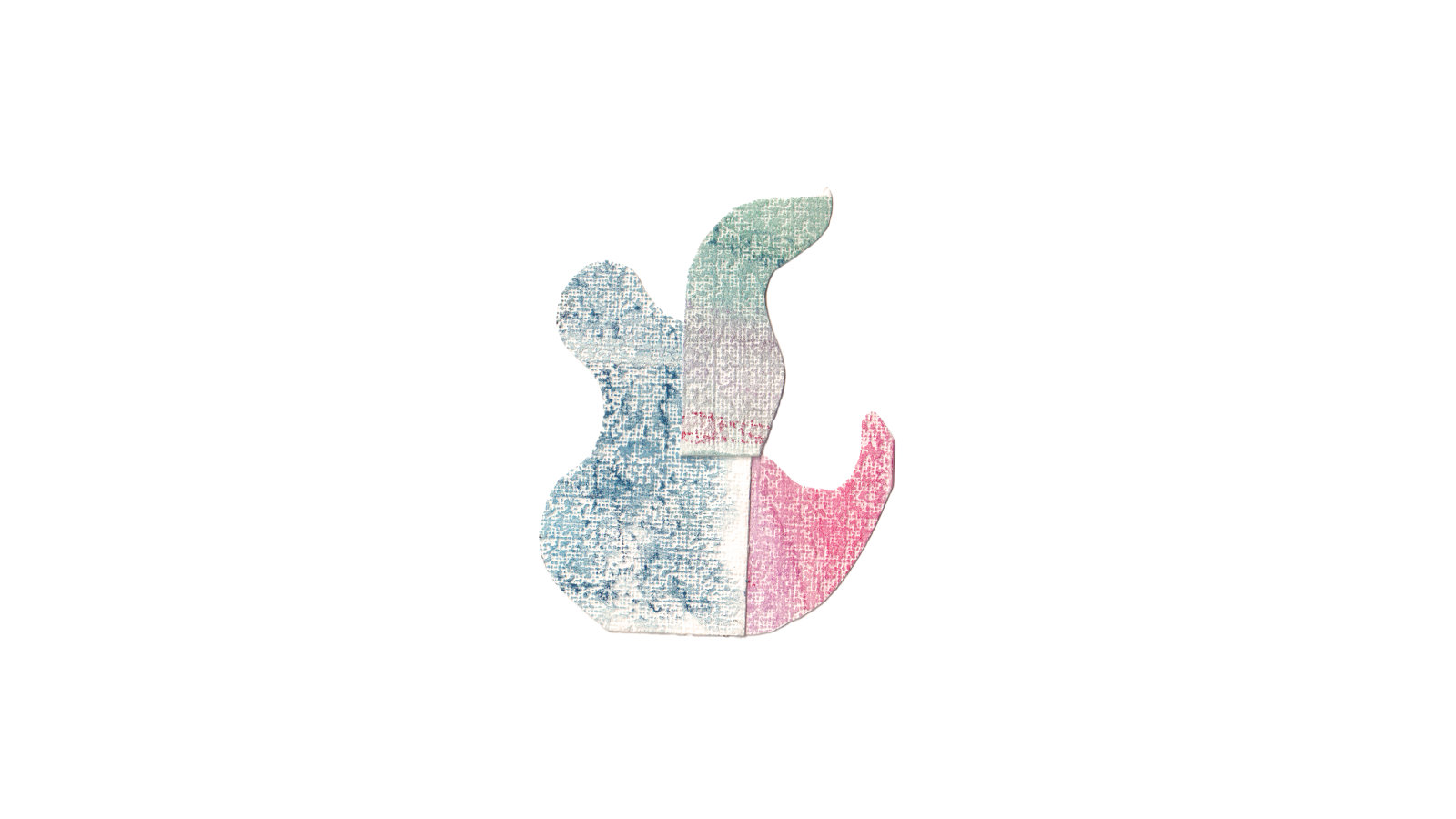
川野太郎(かわの・たろう)
翻訳家・作家。1990年熊本生まれ。訳書にシオドア・スタージョン『夢みる宝石』(筑摩書房)、ベン・ラーナー『トピーカ・スクール』(明庭社)ほか。2025年3月、はじめての散文集『百日紅と暮らす』(Este Lado)を刊行。
artwork / collage | 川野太郎
波と楽器のあいだ/1
夏の手紙
波と楽器のあいだ/3
遠い星