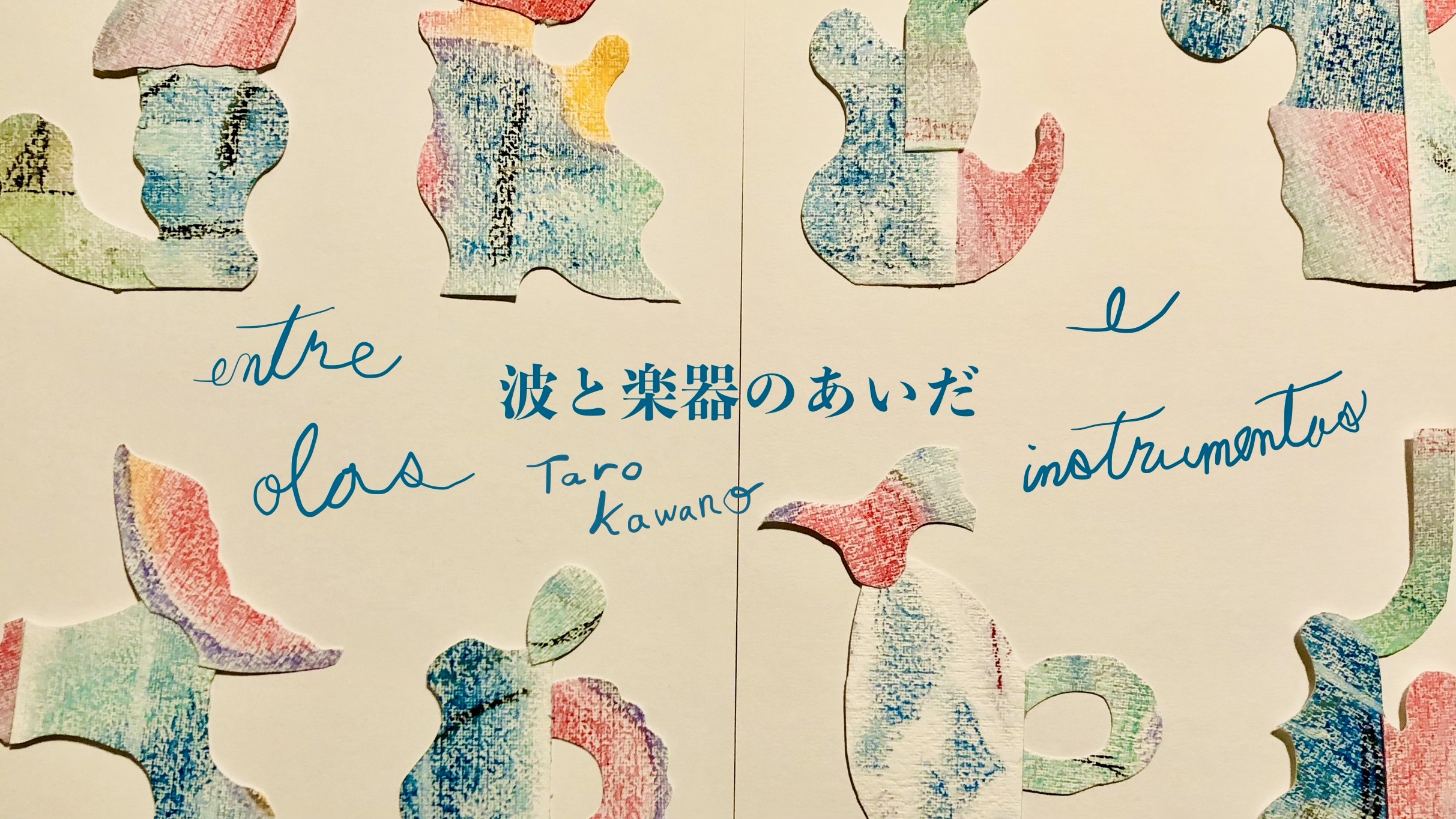
川野太郎
波と楽器のあいだ / 0
2025年7月23日
みんなでビールを
五月、そのとき佳境にさしかかっていた本の翻訳を直しているとき、友達のムギタさんからLINEがきた。
「チャリチョコの英語版いらないよね?」
「チャリチョコ? 初耳単語」
あ、ごめん、いま散歩してたら通りかかった古本屋さんの店先に『チャーリーとチョコレート工場』のペーパーバックがあったの。
ぼくはロアルド・ダールの本の原書を探してはいなかったが、いつかダールが好きだと、とくに『少年』は何度も読んだと話したことがあったかもしれない。
ムギタさんが種明かしをする前にぼくには自転車に乗ったチョコレートが見えていて、すぐにスケッチしたので、彼は消えずに残った。

それどころか、茶菓子を持ってたまにうちに来るようになった。
チャリチョコの自転車のブレーキは甲高くて景気のいい音がする。
「ひといきいれたら」チャリチョコはドアを開けながら言う。
「そうしようかな」ぼくはコーヒーを淹れようと台所に立つ。
「いまなにやってたの」チャリチョコはビニール袋をソファの足元に置いて、ローテーブルの上にあるものを眺める。身を乗り出すとき、首の周りの銀紙がカサカサと音を立てる。
テーブルの上には、赤ペン、青ペン、初校ゲラの原稿、よれよれになったペーパーバックの本。
「訳文の直し。そうやって原稿に赤ペンで修正の指示を入れていくんだけど、読んでるといまだに発見がある」
「いいことじゃないの」
「まあね。発見が尽きないのは読むよろこびだけど、『見落としがあった』ということでもあるから、気づきの興奮とゾッとするのが同時にきて、どうにかなりそうだった、さっきも」
「ふーん、どうかしてるね。あ、どうも」ぼくはチャリチョコのぶんのコーヒーを、ゲラから離れたところに置く。預かっている期間が長めの初校は自分でも気づかないときに汚れてしまうから、気をつけないといけない。
チャリチョコは持ってきたビニール袋の口を開く。「今日はふろ……」
「風呂?」
「フロランタン、だ」
ふたりでしばし明るい茶色のレンガのようなお菓子をつまむ。
チャリチョコは長居しない。コーヒーを飲み終えると自転車にまたがり、近所の中学校に並ぶメタセコイアの緑を伝える初夏の光を銀紙にキラキラ反射させながら漕ぎ去っていく。
チャリチョコがきた日は休憩がうまくいった日だ。十五分とか三十分、休んでいるあいだはそれまでやっていたことを考えず、またはじめるときは少しすっきりした頭でとりかかる。そうやってちいさな終わりとはじまりをくりかえす。その回数はけっして多くなかった。よくなにかを飲み食いしながらも作業の手を止められなかったり、一度休むとうっかり一時間寝てしまったりした。
五月はそんなふうに過ぎていった。
*
六月のはじめ、原稿がひと区切りついたころ、昔からの知り合いから高知のクラフトビールの詰め合わせが届いた。さっそく一本飲んでいるとき、「何本かはだれかと飲みたいかも」と思った。
数日後、ちいさい保冷バッグにビールと保冷剤をつめて、ムギタさんの家にお邪魔した。夕方はやくに最寄り駅から歩くときは曇り空で、線路沿いにあるマンションの前の植え込みに梅雨葵が二本だけ、支柱に絡まりながらぽつんと立っていた。
ビールの横の大皿に盛られていたのは、ミニトマトとモッツァレラチーズとゴールデンキウイ、ベランダのプランターから摘まれたパセリ。
ビールを飲みながら、ムギタさんにチャリチョコのエピソードを読んでもらった。短い小説の連載を依頼してもらったということも話した。
ひとに読まれている、というだけで、感想をもらわなくても、自分の書いたものをいくらか新鮮に眺めることができる。
あらためて、不思議だな、と思った。はじめこそ現実にいた人も想像された人も、紙の上ではもう、はっきりとした違いがないことが。
「しじょうの友、だね」チャリチョコがビールの栓を開けながら言う。
「至上か」
「や、『紙上』って言ったんだ。どっちでもいいけど」
「いいじゃんこれ。続きものにするの?」ムギタさんが原稿から目を離しながら言った。
「考え中」とぼくは言った。
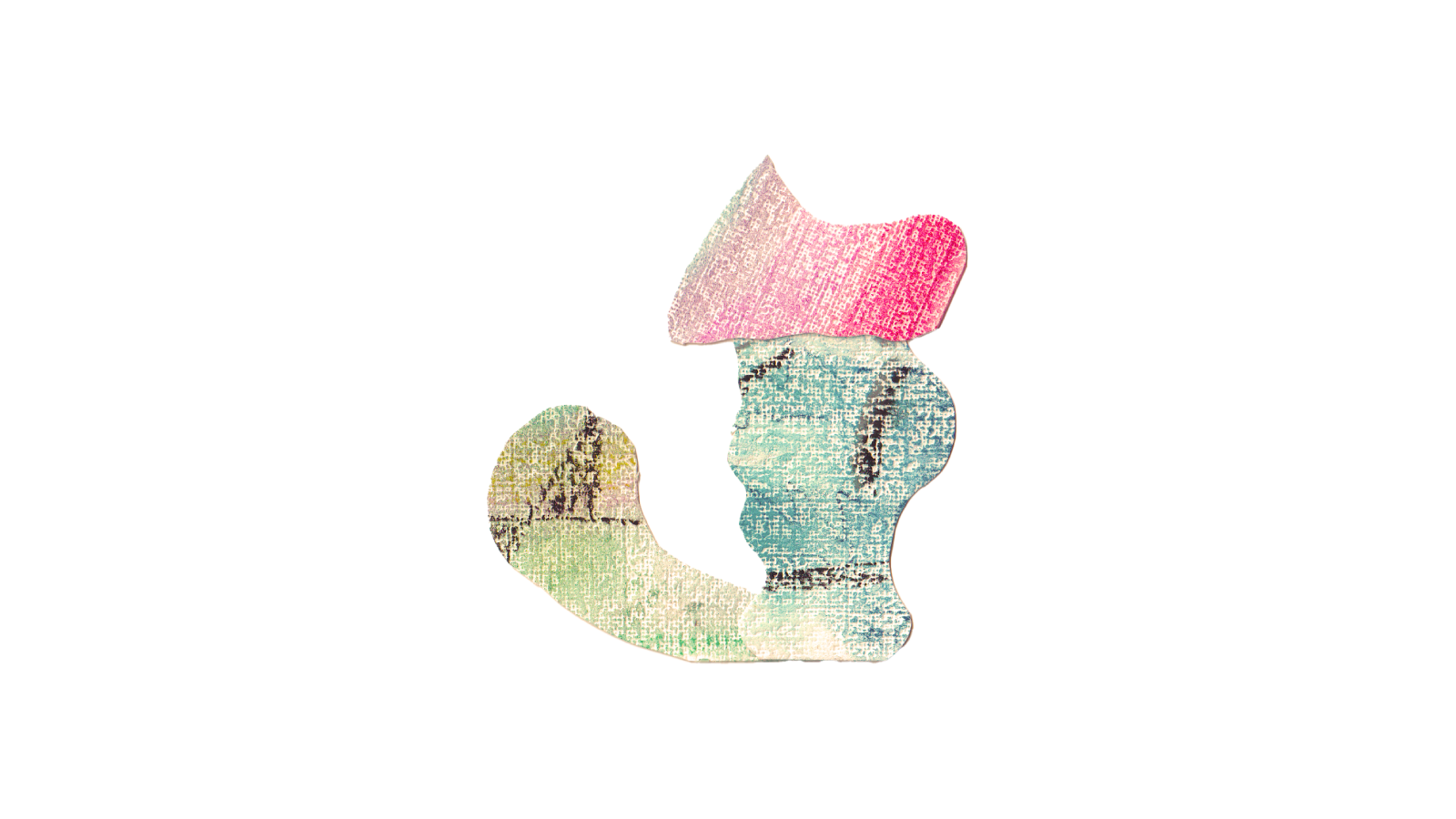
川野太郎(かわの・たろう)
翻訳家・作家。1990年熊本生まれ。訳書にシオドア・スタージョン『夢みる宝石』(筑摩書房)、ベン・ラーナー『トピーカ・スクール』(明庭社)ほか。2025年3月、はじめての散文集『百日紅と暮らす』(Este Lado)を刊行。
artwork / collage | 川野太郎
波と楽器のあいだ/1
夏の手紙