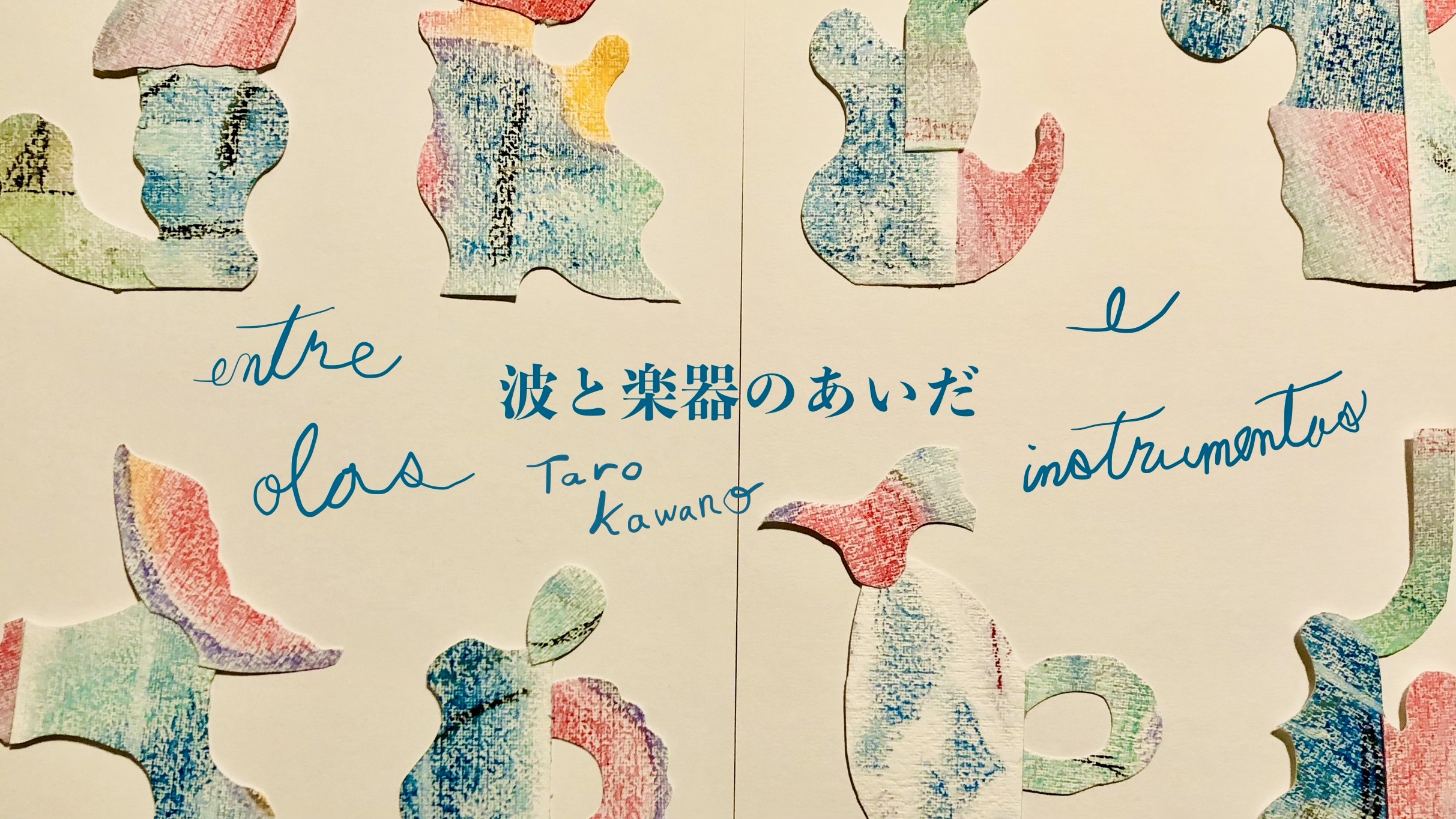
川野太郎
波と楽器のあいだ / 6
2026年1月12日
魔法
ここ十年の年末に比べて、憂鬱はすこし小さかった。ふたりがけのソファのひとり分のそのまた半分のスペースをすべては埋めない程度の
過ごしかたをちょっと変えたからかもしれない。
十代を過ぎた頃から、だいたい年末はついていなくて、ひとと喧嘩になったり、家族のだれかが大きく体調を崩したりする年もあったし、目立った出来事がなくても、なにか重苦しい空気が漂うのだった。
自分にとって年越しがそんなふうであることにはなにか理由があるのだろうが、焦ってつきとめようとせずに、この一日をしのぐのに注意を傾けたい、と思ってきた。
ここ五、六年、そのしのぎかたは、「大晦日から翌日の午前零時をまたぐまでずっと書く仕事をする」というものだった。油断すると年末にすむ魔物にやられると思っていたので、書くことで自分の意識を「オン」にして対抗する、という感じ。けっこううまくいっていた気がする。おかげで沈み込むような落ち込みは来なかった。ずっと緊張してはいて、快適とはいえなかったけれども。
今年はそんな過ごしかたに疑問をもった。以前に何度か重なった年末の不運に追いつかれたくないあまりに、悪い魔法にかかっていたんじゃないか? 身体がルールでこわばっているようだ。
「年越しはぜったいに仕事をしながら」とは決めないようにしよう。完全にだらけるのも得意じゃないけど、どうしたいかはそのつど自分の身体に聞こう。三六五日の最後の日ではあるけど、ただ「この一日」の最後の瞬間でもあるのだから、そのときどきに決めてもいい。
どう過ごしても、この年の瀬にきみのなにかは燃え尽きて、来年また復活するだろう。
そう思いながら大晦日に向かうここ数日を以前よりも柔軟に過ごしたら、緊迫感はやわらいだ。かといって憂鬱がやたらと大きくなったりもしなかった。彼は紫色の身体でぼーっとしているように見える。
「いいね!」と言ったのは暇つぶしに来て本を読んでいたチャリチョコだ。彼の大きさは憂鬱の二倍はあって、ソファの憂鬱のとなりに座っていた。読んでいたのは中井久夫の「荒川修作との一夜」というエッセイ。ぼくが最近読んで「これは!」と思った文章だ。
精神科医の中井久夫は、かつて大学の同僚だった京都大学の木村敏教授に急に呼び出されて、ふたりでニューヨークから来たばかりの画家、荒川修作と面会する。荒川はふたりに、マルク・シャガールのアトリエにしばらくいたときの話をする。
「『シャガールはね』」と荒川は語る。「『朝早く、アトリエに来て、鉄のパレットを取り出す。九十四歳の彼が鉄のパレットだぜ。そこへ色を盛り上げ、カンバスにどしどし色を塗る。たいへんな仕事量だ。そして、夕焼けがアトリエの窓を染めると、部屋じゅうをくまなく掃除し、雑巾をかけ、パレットをきれいに洗って、さあ帰ろうという。ある時、見かねてオレがやると言ったら、じいさん何と言ったと思う? 俺を殺す気か、これをやってるから俺は今まで生きているんだとね、で、またごしごしさ』」。この話を聞いた中井は思う。「いい話であった。私の大好きなライナー・チムニクの童話『クレーン男』のように、日々の力を信じて愚直に生きること――」
「それでおまえも夜の皿洗いをまじめにやってるの?」とチャリチョコが言った。
夜、よっぽどのことがないかぎり台所に洗い物を残したまま寝ないのはこれを読む前からだけど、「荒川修作との一夜」はその習慣の力を確信に変えた。真剣さが変わったと思う。夜になったら一度は仕事を切り上げよう、朝も換気からはじめてみよう、と。
呼び鈴が鳴った。
「遊びに来たよ」厚手の白いコートを着た友達のムギタさんの足元に、なにかカラフルなものたちがうごめいていた。ムギタさんの膝丈くらいのものたちが。「ここに来る途中でついてきたんだけど、なんか川野くんの知り合いだっていうから」
小さい人たちは数えたら総勢十一人いた。姿もさまざまで、ファンタジー映画から出てきたような連中だった。布で目隠しして弓矢を持っている者、大きなつばが波打つ帽子をかぶっている者、旗のついたトランペットを吹いている者、床に引きずるような長いローブを着ている者たちがいた。
肌がうっすら青みがかった、素っ裸の者も三人いた。
「知らない」
「え、まじ」
台所に立ち、総勢十四人でごちゃごちゃした居間を視界の隅で盗み見ながら大きい鍋でお湯を沸かしていると、ムギタさんについてきたひとり、両手にそれぞれカンテラと杖を持っていた小さな髭の者が、カンテラを床に置き、ぼくのズボンをつまんでひっぱった。こちらを見上げる彼に、
「どうだったね今年は」と尋ねられたとき、すべて思い出した。
今年の一月三日に「年始といえば占いだ」と思って、タロットカードで来たる一年の過ごしかたを尋ねたのだった。いまは彼らがカードの枠から出て入り乱れていたので、すぐにはわからなかった。東西南北に一枚ずつ、中央に一枚、計五枚で占った、その五枚のなかにみんないた。
「占いの中身はどんなだったの?」とムギタさんが尋ねた。
「ぜんぜん覚えてない」
占ってから今日までのあいだ、その中身を思い出したことはなかった。尋ねたのが「これからの一年」のことだったとしても、占いはその日のうちに役割を終えていたらしい。それは今年の一月三日をしのぐ方法のひとつだった。カードのなかにいた彼らは、自分たちがあらわれたその日が終わると仕事が終わったと判断し、図像の外に出て、暗示も予言もしない身体で今日まで世界をぶらついていた。
*中井久夫「荒川修作との一夜」、『中井久夫集3 世界における索引と徴候』所収、みすず書房、2017年、p.202。
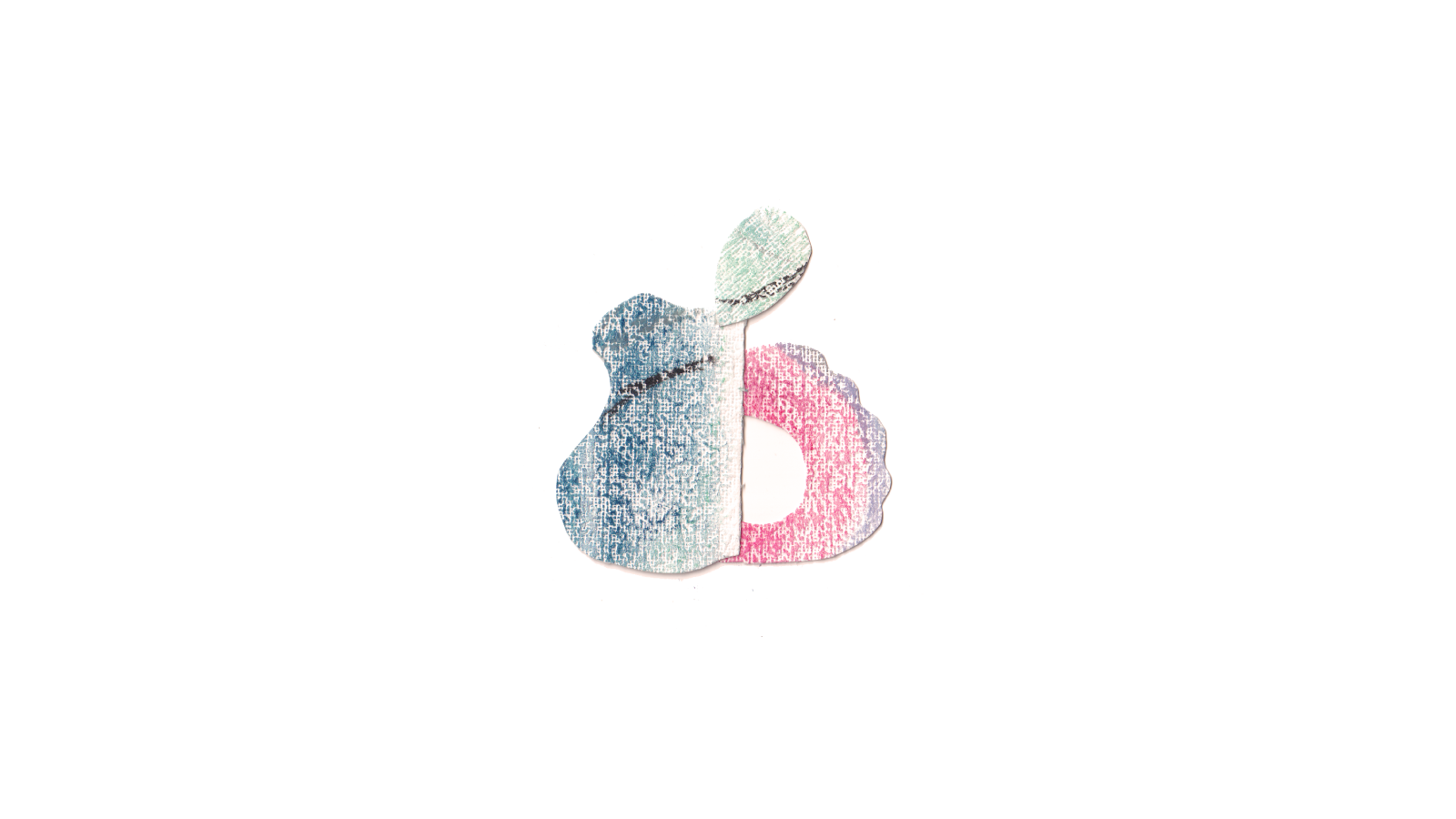
川野太郎(かわの・たろう)
翻訳家・作家。1990年熊本生まれ。訳書にシオドア・スタージョン『夢みる宝石』(筑摩書房)、ベン・ラーナー『トピーカ・スクール』(明庭社)ほか。2025年3月、はじめての散文集『百日紅と暮らす』(Este Lado)を刊行。
artwork / collage | 川野太郎
波と楽器のあいだ/5
ダンス